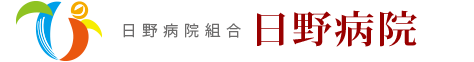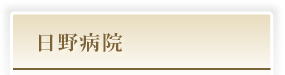「静かなる医療崩壊」の始まり -令和7年5月
鳥取県ではいま、人材不足と医療機関の経営悪化という〝見えない危機〟が進行しています。日野郡にお住まいの皆さんはまだその深刻さを実感されていないかもしれません。それは現在のところあまり困ることはなく充分な医療を享受できているからです。これまで鳥取大学医学部がこの小さい県に多くの医師を送り出し、看護師も多くの看護学校で養成されてきたからにほかなりません。しかし、近年は鳥取に残る医師や看護師はどんどん減少しています。県内では医師の高齢化、若手医師の減少が顕著です。若者の都市流出は続き、地域として彼らを惹きつける魅力づくりについては、親世代や鳥取県の医療 機関、県庁の努力が足りないのも一因だと思います。医療機関に働く私たちは、住民の皆さん以上に強い危機感を抱いています。今年、鳥取県で初期研修を受ける若手医師はわずか36人。私が医師になった頃の半分以下です。長期的に減少傾向が続いており、このままでは、10年後に地域医療を支える人材が足りなくなるのは明らかです。この問題は、大学・病院・行政、そして住民の皆さん一人ひとりが「私の問題」として動かなければ解決しません。住民の皆さんが医療者に対して敬意と感謝を持ち、支える気持ちが医療の未来を守る力になります。
私たち医療者も、患者さんに敬意を払って接し、信頼関係を築き続けたいと思います。
次の問題は経営の悪化です。2024年度は、日本の病院の6割が赤字、自治体病院に限ると8割が赤字です。日野病院は幸いなことに、2024年度も黒字を維持することができましたが、その額は数年前と比 べて激減しています。どうしてでしょうか。実は収入は少しずつではありますが増加しており、これは職員の努力の結果です。しかし、支出がそれ以上に膨らんでいるのです。最近の物価高騰と国が要請している賃上げによる人件費の増加、加えて昨年の診療報酬の引き下げが主な原因です。医療機関は定められた価格で医療を提供します。人件費の増額分や物価上昇分を価格に転嫁できません。しかも、昨年の診療報酬改定によって収入が減少しました。全国の多くの自治体病院が危機的状況に追い込まれました。賃上げを要請するのであれば、その原資として診療報酬をあげるのは当然と思いますが、逆に下げているのは病院を潰しにかかっているとしか思えません。国は将来の人口減少を見越して、病院数 を減らそうとしているようにみえます。しかし、本来自治体病院はsafety netであるべきです。火災がなくても消防署が必要であるのと同じように医療も住民の健康を守るために不可欠です。国の施策はいつも犠牲者が出てからでないと正しい方向に向かわないように思います。命を守る仕組みは、「もしも」に備えるところから始まります。
さて、新年度からの新たな職員についてお知らせします。内科に2名の若手医師が赴任しました。奥谷はるか医師と津田晴宣医師です。ともに学生時代から日野病院で実習され、奥谷先生は研修医としても勤務されたことがあります。今後、住民の皆さんに信頼される医師になっていただけると確信しております。また、新卒を含めて5名の看護師を迎え ることができました。将来の日野病院を支える人材に育つことを期待しています。
最後に職員表彰についてです。今回は病院長賞を磯江光代看護師長が受賞されました。磯江師長は人手不足の中、自らが手本になるような働きをされ、病棟における看護提供方式の改善によって、よりいっそう患者さんに寄り添う看護を実践しました。また、手指消毒使用量向上への 取り組みを組織風土との関連を通じて研究し、学会および論文発表を行いました。局長賞には同じく看護提供方式の改善に尽力した妹尾小百合看護師長、日野郡栄養士連携会議の再開に努力された管理栄養士の白岩幸水恵さん、サルコペニアの研究を学会、セミナーで発表し、学生教育にも貢献した理学療法士の佐田山晋佑くんが受賞しました。これからも一層日野病院の発展に貢献していただきたいと思います。